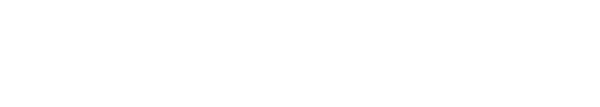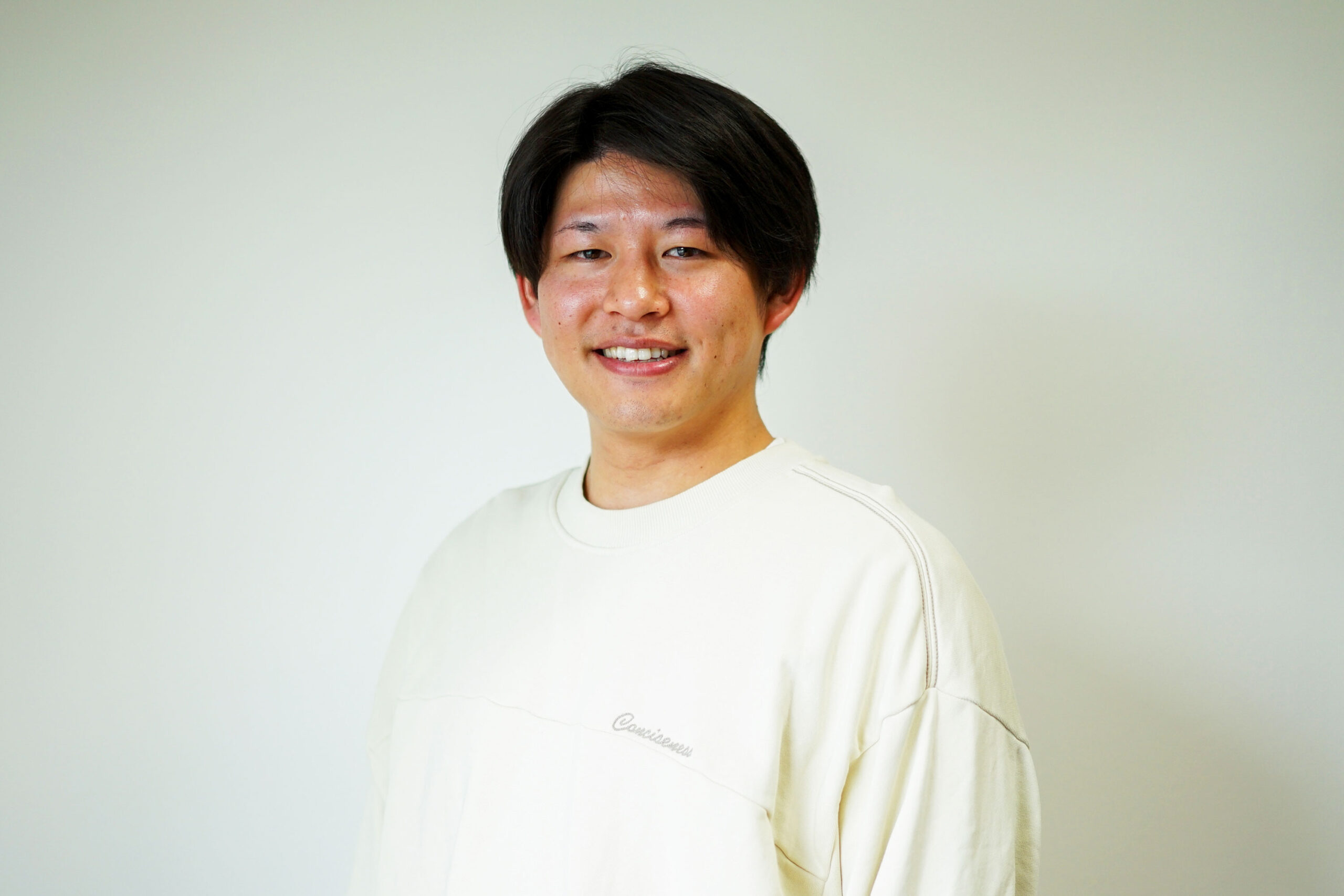チーム効力感が高まり、オープンな横のつながりの構築も実現。Heart Beat PROGRAMを通して、パーパスを体現する組織文化が生まれはじめている。
株式会社明光ネットワークジャパン 常務取締役・DX戦略本部長
Go Good株式会社 代表取締役社長
谷口康忠さん
組織のパーパス浸透、チーム効力感向上のために「Heart Beat PROGRAM」を導入
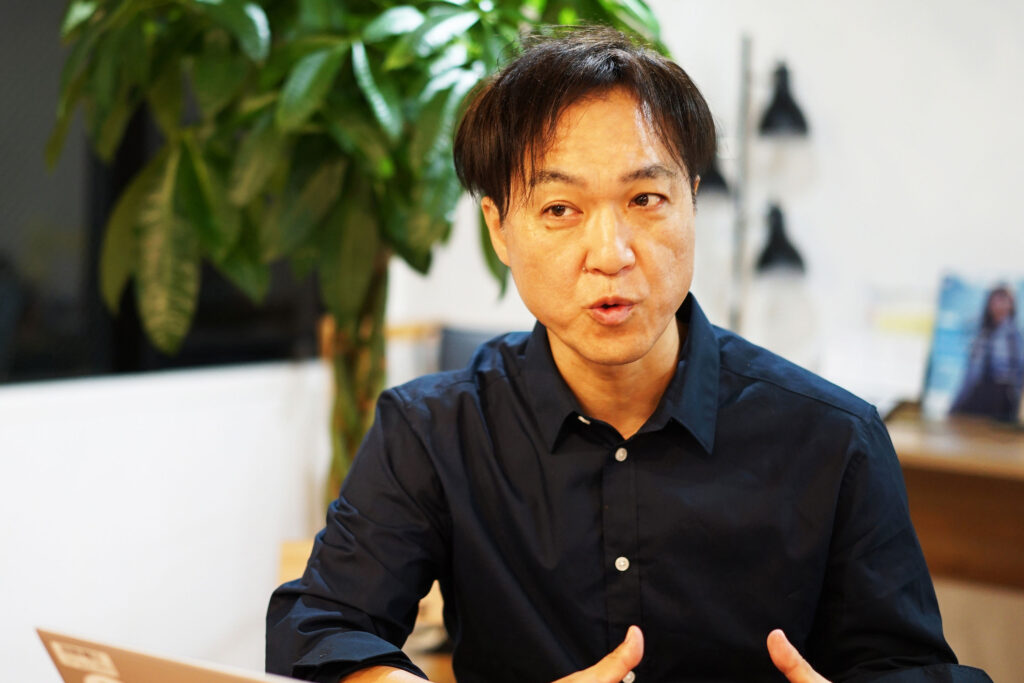
──まずは御社の事業内容についてお聞かせください。
明光ネットワークジャパンは、1984年に日本初の個別指導として明光義塾を展開してから2024年で40周年となります。現在、企業グループとして17社のグループ会社を構えており、個別指導の『明光義塾』だけではなく、学童の『明光キッズ』であったり、上場企業では珍しい日本人学校を所有していたりと、多角的に事業を展開しています。
──そもそも御社ではどのような課題・目標があったのでしょうか?
この40年間において『明光義塾』を中心に会社は非常に大きく成長したのですが、コロナ禍以降は少子化や労働生産人口の減少、教育格差など学習塾を取り巻く多くの社会課題に直面しました。
ただ、本来であればネガティブな要素になりうるこれらの社会課題ですが、われわれ明光ネットワークジャパンは、この40周年を機にこの問題を新たなビジネスチャンスと捉え、転換期であると前向きに受け止めています。
今年、弊社は新たな中期経営計画『明光トランジション』を掲げ、2つのトランジション(変化)を目指すのですが、そのひとつは教育事業会社から総合的な人材支援グループを目指すという『ビジネスのトランジション』。そしてもうひとつが、従来の固定概念にとらわれない一人ひとりのトランジションを図るための『ヒューマントランジション』です。
──スキルだけではなく、人の成長というところに着目をされているのですね。
はい。もちろん、社員のデジタルスキルアップは必要で、会社としてもデジタル経営を意識したDXはこの3年間で加速させてきました。その一方でDXの”X”の部分である『トランスフォーメーション』、いわゆる変革が実はもっと重要ではないかと考えています。例えば、われわれは現在約10万人の生徒さまに通っていただいていますが、データに基づくデジタルを活用した教室業務の変革や新規事業への変革には、『社員自身の変革』や『自己効力感の向上』、そして『チーム効力感の向上』がまずは必要になると思っています。
──谷口様が統括されているDX戦略本部では、どのような目標を掲げているのでしょうか。
弊社のパーパスである『やればできるの記憶をつくる』にもある通り、『私ならできる』という自己効力感がなければ、せっかく身につけたデジタルスキルも活かしきれません。ですので、DX戦略本部としては個人のデジタルスキルはもちろんですが、個々の自己効力感を高めること、『私たちならこの目標を達成できる』『私たちは組織を変革できる』というチームとしての効力感の向上を目指しています。
組織文化の形成こそが、メンバーがワクワク働くための原動力となる

──この度、組織形成や人材育成をサポートするCUOREMO社のサービス「Heart Beat PROGRAM(以下、HBP)」を導入いただきましたが、導入の背景をお聞かせください。
DX戦略本部という組織が ちょうど今年で3 年目になるのですが、先ほどお伝えした”ヒトの変革”という課題に直面した時、『やればできるの記憶を作る』というパーパスをしっかりと体現できるような組織文化を作りたいと考えるようになりました。
組織文化というと非常に曖昧で可視化することが難しく、例えば創業者が作り出した雰囲気そのものであったり、企業のDNAや空気感といった、暗黙知のようなものであったりします。ですが、チーム効力感をしっかりと高めることによってパーパスを浸透させつつ、相互理解を体現できる土台を形成すれば、その先に組織文化づくりも実現できるのではないかと考え、HBPの導入を決めました。
──御社のような大きなレガシー企業ともなると、組織文化の形成は非常に難度が高いようにも思われます。
まさにその通りです。まずは部署内の小集団がそのような意識を持たなければ、なかなか最終的なチーム効力感には行きつかないと思っています。パーパスのような会社の存在意義は非常に重要ではありますが、このチーム効力感を生み出すにあたって、企業のパーパスの浸透はあくまでも手段でしかありません。その手段をしっかり見据えながら、チーム効力感を向上させるために小集団ごとの相互理解を育むことがとても重要であると認識しています。
──その始まりとなる小集団こそ、DX戦略本部だったのですね。
そうですね。これはわれわれの会社に限ったことではありませんが、例えば弊社の場合、『明光義塾』事業の他にも、先ほどお伝えした通り事業が多岐にわたるため、どうしても各事業部長を筆頭とした縦割りの組織になりがちです。その一方でDX戦略本部というのは、マーケティングや情報システム、オペレーションなど、全社共通業務を担う点において、この縦割りの組織に横串を刺して、いわば会社としての基盤 / プラットフォーム的な立ち位置でなければなりません。
部門ごとにそれぞれのやり方がある中で、他部門を巻き込み業務変革 / 事業変革を行っていくということは、他部署との深い相互理解が必要になってきます。日々の業務で手いっぱいの中で組織間連携を行うのはなかなか難しいことではありますが、だからこそ今回まずはDX戦略本部を中心に、われわれの組織からパーパスの浸透やチーム効力感のアップ、そしてその結果、良い組織文化の形成につながればいいなと考えました。
──今回は、各部門から集めたネクストリーダー層向けにパーパスの浸透やチーム効力感の向上をテーマとして研修を実施いたしました。研修の内容は率直にいかがでしたか?
計7回のプログラムを3カ月近くにわたり実施した大きな研修プロジェクトでしたが、研修を通して参加者がどんどん和気あいあいとオープンマインドになっていることを日々感じていました。同じ組織で働いているにも関わらず、企業であるがゆえに他人への興味が希薄になってしまい、他部門にあまり関心を示さない社員は少なくありません。そういった問題もしっかりと研修を通じて解決できたと考えています。組織内の横のつながりを強化する、水平的関係の構築ができました。
──そして、目指していたパーパスの浸透は実現できましたか?
この研修でパーパスの浸透や部門間での相互理解は格段に進みましたし、その先に目指した組織文化を生み出すことができるということも確信できました。
実は、今回の研修を行う前も、パーパス対話会などを通じてパーパス浸透への取り組みは幾度となく行ってきました。しかし、私自身もそうですが、社員自身がパーパス体現のために”具体的にどう行動すればいいか”を理解することにどうしても繋がらなかったんです。 ですが、今回の研修を通してそこを繋げることができたように感じられます。プログラムを重ねる中で、会社の理念と自己理念がうまく紐づけられていったのではないでしょうか。
──課題であった自己効力感の向上やチーム効力感の向上はいかがでしょうか?
こちらも、研修後のアンケート結果にも出ていますが、効果があったと感じています。現代は若手社員に限らず、『自分を理解してほしい』という想いを持つ人が多いようにも思われますが、そのような時代においてはしっかり自己理解をしてオープンマインドで自分をさらけ出し、そしてそれを周囲が受け止めてくれる、そういった相互信頼の構築がすごく重要なのだと改めて実感しました。
定量的なアンケート結果、そして現場で見えるメンバーの具体的な変化を通じて「Heart Beat PROGRAM」の価値を実感

──お話にも挙がった研修実施前後のアンケート結果では、定量的な数値でもポジティブな結果が出ていました。特に、「この会社でワクワクしながら働くことができていますか」というスコアが大きく上がっていますね。
はい。この『ワクワク働く』ということってとても重要ですよね。自分の経験値でものを語るのはあまり良くありませんが、個人的に半径5メートル圏内の人間関係でストレス値は大きく変わると思います。そういった意味で、研修を通じて相互理解が深まるとワクワクのボルテージが上がり、より楽しみながら仕事に前向きになれるのではないかなと感じました。
──「会社理念と自己理念が重なっているか」という設問に関しても平均スコアが上がっています。こちらに関してはいかがですか?
今回の研修では、参加者全員が『マイステートメント』を定めて、それを企業理念=パーパスと重ね合わせることをしていきました。企業理念と自己理念がうまくクロスし密接に繋がることで、双方のベクトルを合わせていくことができたのではないかと思っています。
余談ですが、弊社で導入しているタレントマネジメントシステムで、プロフィール欄に”マイパーパス”という項目を作ってみたところ、 研修に参加したメンバーが主体的に記入してくれていたんです。マイパーパスを積極的に書いてくれているということは、自分を客観的にメタ認知できているんだなと嬉しく思いました。
──アンケートにも表れているこれらの変化は、実際に行動などにおいても見て取ることはできましたか?
はい。この研修に参加したメンバーがすごく主体的になったと感じています。実際に、経営会議の場で意見を発信してくれるようになった方もいて、目に見える変化がありました。今回の研修で自己理解・メタ認知が進んだ結果、自分らしさはもちろん 『自分はここで何がしたくて、なぜこの仕事をしているのか』という究極の自己理解やマイパーパス確立に繋がったのだと思います。
──では、相互理解という観点から、メンバーがオープンになっていることを実感するような出来事はありましたか?
実際に会社での会話が非常に活発化し、いわゆる”ワイガヤ”な文化が生まれはじめていることを感じています。今までは廊下ですれちがったりリフレッシュルームで談話したりするところをあまり見ることがなかったんですが、研修を受けた社員同士が談笑をする場面を見かける機会がすごく増えました。 さらに、私自身、常務取締役という立ち位置であるがゆえに立場的に気を遣われてしまうことがあるのですが、役員や上司社員間でもあまり垣根を感じずにオープンマインドで話かけてくれるようになったのは非常に良かったなと思っています。
──研修を通して見えてきた次の課題があれば教えてください。
本来、組織の指示系統で考えると部門長や課長をまたぐのはあまりよくないのですが、今回、研修後のヒアリングを兼ねて参加者全員と1on1をさせていただきました。その際、複数の社員が非常にオープンに会話をしてくれたんです。
例えば、育児休暇明けの時短勤務制度に関する相談をしてくれたり、自分の結婚式といったプライベートの部分までさらけ出してくれたり、私自身、非常に嬉しく思いました。ただその一方で、オープンマインドになった部下に対してしっかり上司がその声を受けとめる仕組みづくりの必要性も感じました。
部下に変革が起きても、上がそれを受け止められないようでは意味がありません。今回の研修はネクストリーダーである主任係長クラスを中心としてチーム効力感向上を目的に研修を行いましたが、相互理解は上司と部下においても重要で、横はもちろん縦の関係性においても必要だと実感しました。次はぜひ、上司のレイヤーに向けての研修をお願いしようかと思っています。
働くことに喜びや意義を感じられる社会をつくり、そして持続可能で調和のとれた成長を目指す会社であるためには…

──時代とともに会社と個人の在り方が大きく変化していますが、今後、HBPは組織づくりにおいてどのような価値をもたらすことができると思われますか?
ひと昔前だと、会社と社員であれば会社の方が力が強く、個人が会社に属するという文化があったと思いますが、今の時代はそれが対等になっています。労働生産人口が減り、転職にしても新卒採用にしても売り手市場になってきている中で、会社が個人の上に立つのではなく対等にやっていかなければならないことを考えると、HBPのような研修は相互理解を構築する上ですごくいい機会になると思います。
──今後、御社の人材育成や組織づくりにおいては、どのようなことを大事にされるのでしょうか。
まず、パーパスの浸透については引き続き会社の使命としてやっていきたいと思っています。ただ、パーパス浸透はあくまで目標達成の手段の一つです。今回の研修を通して、『やればできるの記憶を作る』というパーパスを起点に、チーム効力感を作ることで組織文化生み出していくことができるということを実感しました。この一連の仕組みづくりは、HBPも活用させていただきつつ、しっかりと継続していきたいと考えています。
「Voices 〜お客様の声〜」に戻る
←BACK